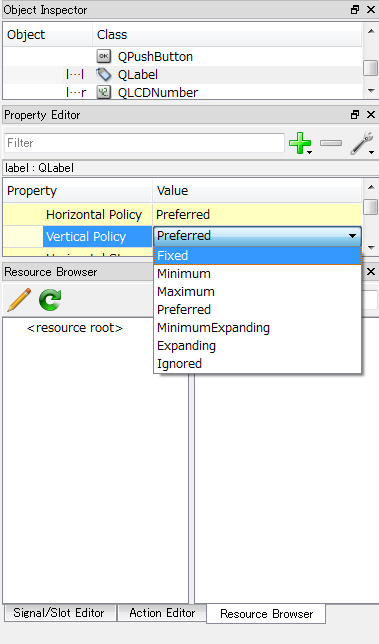さて、Scheme(Racket)でのBrainfuckインタプリタの作成です。
以前にも実は一回書いた事があるってばあるんですが、基本的なエンジンだけの作成で、キチンとしたREPL形式のインタプリタではなかったんですね。今回はキチンとしたスタンドアローンでREPL構造を持つBrainfuckインタプリタを実装してみたいと思います。
Scheme(R5RS)と例外処理
さて、完全なスタンドアローンのインタプリタを作ろう、って場合、例外処理が欠かせなくなります。何故なら入力が正しく行われなかった場合、システムが落ちてしまって、まあ、みっともないから、ですね。
ところで、Scheme(R5RS)互換でBrainfuckを記述しようとすると、大きな問題に次のような事があり得ます。
Brainfuckの場合、インタプリタと言っても、プロンプトに直接コードを打ち込む事はなく(あっても良いけどちとややこしい事が生じる)、基本的にはコードを記述したテキストファイルを読み込んで解釈実行する、ってスタイルです。つまり、REPLの中で「必ず」ファイルを開く動作を定義しなければなりません。
しかしそこでScheme(R5RS)だとややこしい状態が生じるんですね。「ファイルが存在しない」場合の挙動がイマイチ分からない。
つまり、Scheme(R5RS)だと基本的にファイルが存在しない場合はエラーを返し、そいつをまずはトラップすれば良いわけですが、ちとここでSchemeの通知するエラーとは何ぞや、と言う話が出てきます。(with-input-from-file string thunk) 省略可能手続き
string は,一つのファイルを指名する文字列であること。
(with-output-to-file string thunk) 省略可能手続き
そして,thunk は,引数をとらない手続きであること。
with-input-from-file では,ファイルが既存であること。
一方,with-output-to-file では,ファイルが既存だった
ときの効果は未規定である。入力または出力のためにファイ
ルが開かれ,それに接続された入力ポートまたは出力ポー
トが,current-input-port またはcurrent-output-port
によって返される(かつ(read),(write obj ) などで使わ
れる) デフォルト値へと仕立てられ,そしてthunk が無引数
で呼び出される。thunk が戻るときには,ポートが閉じられ
て以前のデフォルトが回復される。with-input-from-file
とwith-output-to-file は,thunk がもたらした(1個ま
たは複数個の) 値を返す。もしも脱出手続きが,これらの手
続きの継続から脱出するために使われるならば,これらの手
続きの振舞は実装依存である。
(open-input-file filename) 手続き
既存のファイルを指名する文字列を取り,そして,そのファ
イルからの文字を配送できる入力ポートを返す。もしもファ
イルを開くことができないならば,エラーが通知される。
1.3.2. エラー状態と未規定の振舞
エラー状態について言うとき,この報告書は“エラーが通知
される” という表現を使って,実装がそのエラーを検出し報
告しなければならないことを示す。もしあるエラーの議論に
そのような言い回しが現れないならば,実装がそのエラーを
検出または報告することは,奨励されているけれども,要求
されていない。実装による検出が要求されていないエラー状
態は,普通ただ単に“エラー” と呼ばれる。
たとえば,ある手続きにその手続きで処理することが明示的
に規定されていない引数を渡すことは,たとえそのような定
義域エラーがこの報告書でほとんど言及されていなくても,
エラーである。実装は,そのような引数を含めるように手続
きの定義域を拡張してもよい。
この報告書は“実装制限の違反を報告してもよい” という表
現を使って,実装の課すなんらかの制限のせいで正当なプロ
グラムの実行を続行できない,と報告することが実装に許さ
れている状況を示す。もちろん実装制限は望ましくないが,
実装が実装制限の違反を報告することは奨励されている。
たとえば実装は,あるプログラムを走らせるだけの十分な記
憶領域がないとき,実装制限の違反を報告してもよい。
もしある式の値が“未規定” (unspecified) であると述べられ
ているならば,その式は,エラーが通知されることなく,な
んらかのオブジェクトへと評価されなければならない。しか
し,その値は実装に依存する。この報告書は,どんな値が返
されるべきかを明示的には述べない。
実はR5RSに載ってる「エラーに関する記述」ってこれだけなんですよ(笑)。あれま。
いや、今まであんま考えて無かったんですが、良く使うエラー提示の"error"って関数も実は存在しなくってあれは実装依存だったんだ、とか今知った所存です(笑)。ダメじゃん(笑)。
つまり、R5RSに関する限り、「エラーを投げる」って事自体が実装依存にならざるを得ないんですね。こう言う事です。
- 自分で書いたコードに於いてエラーを通知する手段が用意されていない
- Schemeシステムが投げるエラーをトラップする手段がない
例外処理、と言うのは基本的には「出てきたエラーに対して適切な手段を提示する」わけなんですが、R5RS範疇では「どういうエラーが提示されてるのか」判別する手段が無い。つまり、この辺りは全部Schemeの下のレイヤーで決定されてる、って事になります。
例えばRacketの場合だと、存在しないファイルを開こうとすると、
なんて返してくるわけですが、一体これをどうやってトラップするのか?Racketだとexnと言う構造体が定義されていて、それを利用してこの場合、exn:fail:filesystem:errnoと言うブツを返すらしいんですが、こんなのが他のシステムにも採用されてる保証はない(Pythonみたいに例外クラスをOOPで定義されてる場合も当然あるでしょう)。これはSRFI34、SRFI35、SRFI36とか使っても本質的に解決出来る問題だとは思えないのです。
つまり、この辺がR5RSのポータビリティの限界ですね(笑)。もちろん上のSRFIなんかでも上手くラップしてるのかもしれませんが、エラー定義がシステムの内部依存になってるとすれば、おとなしく(笑)システム依存の例外処理機構使った方が良さそうです。
何か負けた気もするんですが(笑)、今回は諦めて、例外処理に関してはRacketが提供しているwith-handlersをおとなしく使う事にします(苦笑)。
Brainfuckの仕様
まあ、当然知ってる人は知ってるでしょうが、Wikipediaの方から改めてBrainfuckの仕様を抜書きしてみます。
>ポインタをインクリメントする。ポインタをptrとすると、C言語の「ptr++;」に相当する。<ポインタをデクリメントする。C言語の「ptr--;」に相当。+ポインタが指す値をインクリメントする。C言語の「(*ptr)++;」に相当。-ポインタが指す値をデクリメントする。C言語の「(*ptr)--;」に相当。.ポインタが指す値を出力に書き出す。C言語の「putchar(*ptr);」に相当。,入力から1バイト読み込んで、ポインタが指す先に代入する。C言語の「*ptr=getchar();」に相当。[ポインタが指す値が0なら、対応する]の直後にジャンプする。C言語の「while(*ptr){」に相当。]ポインタが指す値が0でないなら、対応する[(の直後[1])にジャンプする。C言語の「}」に相当[2]。
さて、Scheme的に言うと1から6までが「関数」(手続き)そして7番と8番は「特殊形式」(構文、あるいはシンタックス)になりますね。実は1から6までは実装はハナクソなんですが、7と8がややこしい。一体これをどうやってプログラムするのか。
今までParser自体は書いた事があんま無いわけですが、要するにRead部分でBrainfuckのプログラムファイルを読み込んだ時点で、どうやらジャンプ先の候補ってのをマーキングしておいて、それを「パーズと称して」(笑)Evalに渡さなければならないみたいです。この辺はEvalでやる事じゃあなさそうですね。ではやってみますか。
Read の実装
まずはファイルを読み込む関数(read-file)を実装していきます。仕様は次の通りとします。
- ファイルを開く。
- ストリームから一文字ずつread-charする。その度にカウンターを+1する。
- 文字が>、<、+、-、.、,の場合はcodeにconsする。
- 文字が[の場合はlsにカウンターの値をpushする。
- 文字が]の場合はlsの値をpopして、stackにカウンターの値と(car ls)のペア、(car ls)とカウンターの値のペアをpushする(つまり、stackは連想リストとする)。lsに対応する[の位置情報が無い場合、「カッコの数が合致してない」んでエラーを返す。
- 文字がこの8種類以外の場合は無視してread-charする。
- ファイル終端に来た場合、ls内に位置情報が残ってる場合、「カッコの数が合致してない」んでエラーを返す。lsが空リストだったら多値として(reverse code)と連想リストstackの二値を返す。
さて、read-fileを書き上げたら Read 部本体である parser (実際は parse は read-file がやってるんですが・笑)関数を実装していきます。これは今までのゲームの例のように、インタプリタの現状(phase)に合わせて動作を変更します。次が parser の仕様です。
ゲームの場合もそうですが、「受け取った何らかの入力は」 x に束縛して、それ以外 Read は特に何もやりません。唯一の例外は、 read-file に構文解析させた情報を code と stack に積むのみ、だけですね。あとは phase 情報に従って適切な読み込み系関数を探して実行するだけ、となります。
では Eval を見て行きましょう。
と言うのも、今までのゲームと違って、今回の brainfuck インタプリタの場合、全体的にREPLとしてイベントループを形成するのはもちろんですが、一旦コードが読まれると基本的には Eval 内で繰り返し処理してから Print 部に渡す為、 phase がどういうステージを持つのかハッキリしないとちと混乱してくるからです。
(しかも、Eval 自体でのループの際、 .命令と,命令があった場合、一旦ループを中断して、Print部とRead部の助けを借りないとならない)
. では一旦 interp 関数のループを止めて、ポインタの指すメモリの値を Print 部に渡さないとなりません。
手順としては、
- 関数 parser は x、 phase、 counter、 code、 pointer、 memory、 stackの7つの引数を受け取る関数とする。
- parser は phase に従ってその挙動を変えるものとする。なお、phaseの中身は基本的にはシンボルである。
- phase が 'read-file だった場合、ユーザーからプロンプトを通じてファイルパスを受け取り、その引数を関数 read-file に受け渡し、返り値を受け取り、多値としてx、 phase、 counter、 code(これは read-file が返したもの)、 pointer、 memory、 stack(これも read-file が返したもの)の7つを返す。
- phase が 'read-char だった場合、ユーザーからプロンプトを通じて1文字だけ受け取りそれを新たに x として x、 phase、 counter、 code、 pointer、 memory、 stack の7つの値を多値として返す。
- phase が read だった場合、ユーザーからプロンプトを通じて何か受け取り、それを新たに x として x、 phase、 counter、 code、 pointer、 memory、 stack の7つの値を多値として返す。
- それ以外の場合は基本的にスルーして、 x、 phase、 counter、 code、 pointer、 memory、 stack の7つの値をそのまま多値として返す。
ゲームの場合もそうですが、「受け取った何らかの入力は」 x に束縛して、それ以外 Read は特に何もやりません。唯一の例外は、 read-file に構文解析させた情報を code と stack に積むのみ、だけですね。あとは phase 情報に従って適切な読み込み系関数を探して実行するだけ、となります。
では Eval を見て行きましょう。
Eval の実装
まず、Eval の実装を始める前に、インタプリタの動作の振る舞いを決定するステージ、 phase がどんなものになるか決めてしまいましょう。と言うのも、今までのゲームと違って、今回の brainfuck インタプリタの場合、全体的にREPLとしてイベントループを形成するのはもちろんですが、一旦コードが読まれると基本的には Eval 内で繰り返し処理してから Print 部に渡す為、 phase がどういうステージを持つのかハッキリしないとちと混乱してくるからです。
(しかも、Eval 自体でのループの際、 .命令と,命令があった場合、一旦ループを中断して、Print部とRead部の助けを借りないとならない)
- introduction ステージ: インタプリタを起動した際にアプリケーションが自己主張するステージ(まあ無くても良いんですが・笑)
- read ステージ: 何らかの入力を外部から読み込むステージ
- read-file ステージ: Brainfuck プログラムファイルを読み込むステージ
- read-char ステージ: 一文字だけ入力を外部から読み込むステージ
- put-char ステージ: 一文字だけ表示するステージ
- execute ステージ: Brainfuck プログラムを評価するステージ
- break ステージ: 何らかのエラーによってプログラムの実行が中止されたステージ
- exception ステージ: エラーに関する表示を行うステージ
基本的には上の8つとなります。
それで、ステージがイベントループの中核になるわけですが、基本的な流れは
introduction -> read -> read-file -> execute -> read -> read-file -> execute -> ...
と言うカンジで、初回だけ introduction が出てきますが、あとは read -> read-file -> execute -> の繰り返しです。 execute 内でたまに、read-char ステージかあるいは put-char ステージが求められる、と言う考え方です。
なお、break ステージだけは Eval が設定しません。これは後で例外処理機構が例外を処理した際に設定するステージとしましょう。それを Eval が見て、exception ステージを設定する、と言う考え方で実装します。
では以下に Eval の簡単な仕様を提示します。
- Eval(interp 関数) は x、 phase、 counter、 code、 pointer、 memory、 stack、の7つの引数を受け取る関数とする。
- phase が 'introduction だった場合 phase を 'read に変更し、x、 'read、 counter、 code、 pointer、 memory、 stack、の7つを多値として返す。
- phase が 'read だった場合、
- x(入力値)がquit、exit、または bye だった場合、brainfuck インタプリタを終了する。
- x が load、 open、 または read-file だった場合、phase を 'read-file に変更し、x 'read-file counter code pointer memory stack の7つを多値として返す。
- それ以外の場合はスルーして、 x、 phase、 counter、 code、 pointer、 memory、 stack の7つを多値としてそのまま返す。
- phase が 'read-file だった場合、BrainfuckコードがRead部から読み込まれた事を意味する。すなわち、phase を 'execute に設定し、再帰的に自身を呼び出す。具体的には x、 'execute、 counter、 code、 pointer、 memory、 stack、を7つの引数として interp 関数を呼び出す。
- phase が 'read-char だった場合、pointerが指すメモリの値に 入力値 x を整数に変換した値を足して、phase を 'execute に変更して自身を呼び出す。
- phase が 'put-char だった場合、出力が終了した事を意味する。従って、phase を 'excute に変更して自身を呼び出す。
- phase が 'execute だった場合、次のように動作する
- counterの値がcodeの長さと一致した場合、Brainfuckコードの解釈実行が終了した事を意味する。すなわち初期化として #f、 'read、 0、 #f、 0、 '(0 . 0)、 '()、の7つを多値として返す。
- 1でなければ counter の指す code の値を解釈実行する。すなわち、Brainfuckの仕様に従って動作する。
- phase が 'break だった場合、phase に 'exception を設定して、x、 'exception、 counter、 code、 pointer、 memory、 stack、の7つを多値として返す。
- phase が 'exception だった場合、Brainfuckインタプリタシステムがエラー報告をユーザーに行い終わった事を意味する。従って初期化として #f、 'read、 0、 #f、 0、 '(0 . 0)、 '()、の7つを多値として返す。
- それ以外の場合は phase に 'introduction を設定して、x、 'introduction、 counter、 code、 pointer、 memory、 stack の7つを多値として返す。
これが基本動作です。
さて、実際はもっと具体的に5-2がどういう事を行うか、なんですが、ちょっと説明しましょう。
基本的には「全く破壊的操作を行わない」Brainfuck仕様を考えています。Wikipediaの説明を見ると、Brainfuckで扱うメモリとは
Schemeには連想リストがあるんで、これをメモリに見立ててみれば良い、と言う事です。
つまり初期値として memory と言う引数には '((0 . 0)) と言う「連想リスト」を与えてます。これは「メモリゼロ番地で、初期値は0」と言う意味合いに対応しています。
>と言う命令を見た時、pointerを1増やすわけですが、その時、平たく言うと memory に '(1 . 0) と言うペアをconsしてやる。そうすれば memory は '((1 . 0) (0 . 0)) と言う状態になって、二つの記憶域を持つ状態になります。もう一回 > があれば今度は memory は '((2 . 0) (1 . 0) (0 . 0)) と言う状態になりますね。
つまり、実質的には > は memoryに (pointer . 0) と言うペアを cons する関数だ、と捉え直す事が出来るのです(もちろん、既にポインタが指すペアが存在する場合は新たにペアを cons する必要はありません)。
+、-は pointer の指す memory を assv して、その cdr に対して加算(+1)ないしは減算(-1)を行います(これを datum とする)。ただし、ここでも破壊的変更を避ける為、memoryから対象のペアを削除して(この削除は破壊的削除ではない)新しく作ったペアを cons します。
さて、実際はもっと具体的に5-2がどういう事を行うか、なんですが、ちょっと説明しましょう。
基本的には「全く破壊的操作を行わない」Brainfuck仕様を考えています。Wikipediaの説明を見ると、Brainfuckで扱うメモリとは
少なくとも30000個の要素を持つバイトの配列(各要素はゼロで初期化される)となってるんですが、そこはSchemeなんで別に上限値を設定する必要はありません。ではどうするのか。
Schemeには連想リストがあるんで、これをメモリに見立ててみれば良い、と言う事です。
つまり初期値として memory と言う引数には '((0 . 0)) と言う「連想リスト」を与えてます。これは「メモリゼロ番地で、初期値は0」と言う意味合いに対応しています。
>と言う命令を見た時、pointerを1増やすわけですが、その時、平たく言うと memory に '(1 . 0) と言うペアをconsしてやる。そうすれば memory は '((1 . 0) (0 . 0)) と言う状態になって、二つの記憶域を持つ状態になります。もう一回 > があれば今度は memory は '((2 . 0) (1 . 0) (0 . 0)) と言う状態になりますね。
つまり、実質的には > は memoryに (pointer . 0) と言うペアを cons する関数だ、と捉え直す事が出来るのです(もちろん、既にポインタが指すペアが存在する場合は新たにペアを cons する必要はありません)。
注: なお、実際はペアを使って cons するのではなく、SRFI1のalist-consを使って cons していきます。反面、 < は「既に > が作成したメモリ」をたどっていくだけなので新しいメモリ(のペア)を作成する事はありません。単純に pointer の値を -1 するだけです。
注: なお、本当は上の機構を使えば負の番地を持つメモリも実装可能ですが、今回は敢えてやっていません。pointer の値が負になるとエラーを返します。
+、-は pointer の指す memory を assv して、その cdr に対して加算(+1)ないしは減算(-1)を行います(これを datum とする)。ただし、ここでも破壊的変更を避ける為、memoryから対象のペアを削除して(この削除は破壊的削除ではない)新しく作ったペアを cons します。
注 : 具体的には、Eval( interp 関数)が引数として memory を保持してるので、再帰過程に於いて SRFI1 の alist-delete を使って対象ペアを除いたカタチで memory を取り出し、それに対して pointer と計算し終わったdatum を alist-cons する。すなわち書式は
(alist-cons pointer datum (alist-delete pointer memory))
となる。
手順としては、
- phase を 'put-char にしてループを抜ける宣言をする。
- (integer->char (cdr (assv pointer memory))) の値を x に束縛して x、 'put-char、 counter + 1、 code、 pointer、 memory、 stack、の7つを多値として返す。
です。
でこっちは滅多にないんですが、,命令も.に似てますね。
- phase を 'read-char にしてループを抜ける宣言をする。
- すなわち、 x、 'read-char、 counter + 1、 code、 pointer、 memory、 stack、の7つを多値として返す。
phase が 'put-char、あるいは 'read-char の場合は既に書きました。基本的には phase に 'executeをセットしなおして自身を再帰呼び出しするだけです。ただし、 read-charモードの場合はメモリに入力値を加算しないといけませんが、前述した通り、SRFI の alist-delete と alist-cons を上手く使って破壊的操作を回避します。
最後はループ命令です。
[を見た時、
具体的な話をすると、 stack も連想リストです。これはRead部でread-fileが解析したジャンプ対象の位置情報が入っています。
例えばBrainfuckの何らかのプログラムの4つ目に[があって、41個目に]があった場合、stackは '((4 . 41) (41. 4))と言うカタチで対応を保持しています。そして実行部である Eval (interp 関数)では、code の4つ目で [ を見た場合 (cdr (assv pointer memory)) の値が 0 であるかどうかをチェックして、そうだった場合、カウンターを一気に41へ(正確には]の後ろなんで42)進めます。
]の場合は、無条件に stack が提示する [ の位置へとカウンターを「戻し」ます。先ほどのケースで、stackが'((4 . 41) (41. 4))だった場合、counterが41なんでcounterを (cdr (assv counter stack)) に従って4に戻して interp 関数は自分を再帰呼び出しします。
と言うわけで、Eval ( interp 関数)のコードは以下の通りです。
では最後にPrint部です。
Print部に直接関連した phase は
まずは大域変数 *messages* を設定します。
1、2、3のケースだと単純に (cdr (assq phase *messages*)) を表示すれば良いだけですし(何のために *messages* のキーと phase の値に互換性を持たせてるのか、と言うとこの為です!)、4、5の場合は Eval ( interp 関数)が渡してきた x を表示すれば良い。あとは、プロンプトを表示するだけなんで、Print 部は次のように簡単に書けます。
これで、BrainfuckのREPL各部位は完成しました。あとは実際REPLとして組み上げるだけです。
平たく言うと、REPL部でそれをやってしまおう、って事です。
まずは、例外処理無しのREPLをひな形として組んでみます。
これでも充分動くんですが、例えば「存在しないファイル」を開こうとすると当然エラーが出てシステムは落ちてしまいます。
システムが落ちる、とはどういう事か。継続よろしく、エラーと言うのは発生するとトップレベルに強制的に戻される(つまり関数内から抜ける)、って事になるわけですね。
つまり、言い方を変えると、例外処理と言うのはトップレベルに戻る前にそのエラーをまずは「捕まえる」仕組みです。そして捕まえたらそのエラーの種類に従って、適切な処置を施す。
この場合、REPL内でエラーが投げられるわけですが、どういう処理が必要かと言うと、大枠的には「REPL内に戻る」事になります。何故かと言うとインタプリタ内でエラーが起きて別のプログラムが走ったりすればこれは困ります(笑)。インタプリタでエラーが起きたらインタプリタに戻って欲しい。
言い換えると
ってのが「エラーに対する適切な処置」になるわけです。
基本的にはどんなエラーが起きてもインタプリタに戻って構わないんですが、一応「どんなエラーが起きたか」ユーザーに示さないといけない(利便性の問題です)。その為に「どんなエラーが起きたのか」知る必要があって、その為のエラートラップになるわけですね。
今まで組み上げたプログラムを見ると(想定された)エラーの種類、ってのは次の通りです。
最後はループ命令です。
[を見た時、
- pointer が指すメモリの値、すなわち (cdr (assv pointer memory)) が0なら stack から counterから飛べる値を探してきて、counter にその値をセットして自身を再帰呼び出しする。
- そうじゃないなら、counterを+1してそのまま処理を継続する。
具体的な話をすると、 stack も連想リストです。これはRead部でread-fileが解析したジャンプ対象の位置情報が入っています。
例えばBrainfuckの何らかのプログラムの4つ目に[があって、41個目に]があった場合、stackは '((4 . 41) (41. 4))と言うカタチで対応を保持しています。そして実行部である Eval (interp 関数)では、code の4つ目で [ を見た場合 (cdr (assv pointer memory)) の値が 0 であるかどうかをチェックして、そうだった場合、カウンターを一気に41へ(正確には]の後ろなんで42)進めます。
]の場合は、無条件に stack が提示する [ の位置へとカウンターを「戻し」ます。先ほどのケースで、stackが'((4 . 41) (41. 4))だった場合、counterが41なんでcounterを (cdr (assv counter stack)) に従って4に戻して interp 関数は自分を再帰呼び出しします。
と言うわけで、Eval ( interp 関数)のコードは以下の通りです。
では最後にPrint部です。
Print の実装
Print部は相変わらず簡単です。単純に言うとメッセージを大域変数で連想リストとして設定して、phase の条件に従ってassvで検索したペアの cdr を表示すれば良い。そしてその後、返り値を返します。Print部に直接関連した phase は
- introduction
- read-char
- read-file
- put-char
- exception
の5つで、そのうち1、2,3は纏められて、4、5も纏められます。
まずは大域変数 *messages* を設定します。
1、2、3のケースだと単純に (cdr (assq phase *messages*)) を表示すれば良いだけですし(何のために *messages* のキーと phase の値に互換性を持たせてるのか、と言うとこの為です!)、4、5の場合は Eval ( interp 関数)が渡してきた x を表示すれば良い。あとは、プロンプトを表示するだけなんで、Print 部は次のように簡単に書けます。
これで、BrainfuckのREPL各部位は完成しました。あとは実際REPLとして組み上げるだけです。
REPL と例外処理
まあ、前からやってる通り、単純にはSchemeのSRFI11を利用して多値関数同士を結んで末尾再帰でREPLを書くだけで良いんですが、各関数(っつーかReadとEval)は場合によっては例外を throw しますが、一方、例外を catch してシステムを安全にする機構は組み上げてません。平たく言うと、REPL部でそれをやってしまおう、って事です。
まずは、例外処理無しのREPLをひな形として組んでみます。
これでも充分動くんですが、例えば「存在しないファイル」を開こうとすると当然エラーが出てシステムは落ちてしまいます。
システムが落ちる、とはどういう事か。継続よろしく、エラーと言うのは発生するとトップレベルに強制的に戻される(つまり関数内から抜ける)、って事になるわけですね。
つまり、言い方を変えると、例外処理と言うのはトップレベルに戻る前にそのエラーをまずは「捕まえる」仕組みです。そして捕まえたらそのエラーの種類に従って、適切な処置を施す。
この場合、REPL内でエラーが投げられるわけですが、どういう処理が必要かと言うと、大枠的には「REPL内に戻る」事になります。何故かと言うとインタプリタ内でエラーが起きて別のプログラムが走ったりすればこれは困ります(笑)。インタプリタでエラーが起きたらインタプリタに戻って欲しい。
言い換えると
エラーが起きた -> でもインタプリタ(REPL)に戻る
ってのが「エラーに対する適切な処置」になるわけです。
基本的にはどんなエラーが起きてもインタプリタに戻って構わないんですが、一応「どんなエラーが起きたか」ユーザーに示さないといけない(利便性の問題です)。その為に「どんなエラーが起きたのか」知る必要があって、その為のエラートラップになるわけですね。
今まで組み上げたプログラムを見ると(想定された)エラーの種類、ってのは次の通りです。
- read-file 内で起きた「ファイルが見つかりません」エラー
- read-file 内で起きた「カッコの数が合いません」エラー
- eval内で起きた「pointerの値が負の数です」エラー
この3つが想定されてるエラーです。1番はScheme(より正確に言うとRacket)組み込みのエラー、2番と3番はプログラマ側が決めたエラーです。
( with-handlers ((述語 エラー処理) ...) (本体))
つまり、まず構文的には、(let-values ... で形成されたREPLの本体を(with-handlers で包んでやれば良い、って事になる。
加えると、述語なんですが、要するにこれがエラー種類を判定する述語です。
先にも書きましたが、1. のケースだとRacket自体が「どういう種類のエラーなのか」定義してる部分で、これはプログラマ側でどーにか変更する、ってモノじゃありません。リファレンスで調べなきゃいけない範疇となります(笑)。で、exn:fail:filesystem:errno ってのがそのエラーの型で exn:fail:filesystem:errno? がその述語になります(ちなみに exn 自体は変数扱いになるようです)。
2番と3番がプログラマ側が定義したエラーで、raise で定義した・・・事実上、定義したエラーになります。何を定義したのか、と言うと raise に与えた引数がその型を定義してる、って言って過言じゃないです。何故 read-file や interp で使った raise にシンボルを引数として与えたのか、と言う理由がここにあります。
と言うのも、シンボルを引数にして与えた raise によるユーザー定義のエラーの場合、述語は単純にラムダ式となって
(lambda (v) (eq? '何かのシンボル v))
と書ける。一般にSchemeを含むLisp族はシンボルはユニーク(単一しか存在し得ない)である事が保証されていて、しかも eq? による比較は高速で決着が付く。これを考えると raise する場合は圧倒的にシンボルを引数に与えた方が得だ、って事になりますね。
つまり、組み込みエラーの場合は ext がシンボルなんでエラー処理部分のラムダ式の引数は ext 、他の場合は自分で決めたもの、例えば述語部位が v を使ってたらエラー処理部分のラムダ式の引数も v にする、って事ですね。
さて、さっきも書いた通り、エラー処理自体は「REPLに戻るのが前提」と書きました。ここで整理すると、
- x はPrint部の為に「こう言うエラーが起きました」と言う文字列情報を入れる。
- phase は 'break にセットする。
- あとの引数は(どの道 Eval が初期化する前提なんで)手を付けない。
- 以上の情報を持ってREPLを再度呼び出す
となります。つまり、エラー処理のラムダ式は原則
(lambda (引数) (repl エラー情報文字列 'break counter code pointer memory stack))
になる、って事を意味します。
これを考慮してREPLを修正します。
これで、仮に「存在しないファイル」をREPLで開いた場合でも、Brainfuckインタプリタは落ちないで、そのまま処理を継続します。
以上でBrainfuckインタプリタの完成です。以下に全コードを載せておきます。
Racket で実行形式作成
以前から Racket には raco と言うコンパイラが付属してたんですが、コマンドラインツールだし、何かメンドくせえし(笑)、とかでスタンドアローンでの実行形式作るのは諦めてたんですね。しかし最近、とうとう DrRacket IDEからメニューから選んで実行形式が作れるようになる、と大進歩を遂げました。Lisp系言語だと「スタンドアローンは作りづらい」って言われてたんですが、ここに来てやっとLispプログラムの恩恵を一般に配布しやすくなった、って言って良いでしょう。
ただ、残念なのは、どうもユニコードの問題があって、日本語なんかの文字列が入ってるとコンパイラが通ってもすぐ落ちたりしちゃうんですね(今回、メッセージ表記を全て英語にしたのはそのせいです)。
ファイルを保存してからDr.Racketの [Racket] メニューから [実行ファイルの作成...]を選びます。
そうするとポップアップメニューが現れます。
Typeに関しては一番下のDistributionを使えば良いでしょう。と言うのも、これがアプリの配布形式を作るブツだからです。
注: 一番目のブツは平たく言うとエイリアスを作るだけで、コンパイルして実行形式を作るとはいえない。二番目はコンパイルは行うが、その実行にはRacket本体が必要で、要するにいわゆる「ランタイム」を含めた実行形式を作成するには3番目のDistributionしかなく、配布目的、あるいは完全なスタンドアローンを作るならこれを利用するしかなくなる。
BaseもRacketを使えば良いです(GRacketはRacket(コマンドライン版)のちょっとしたGUI版程度です)。
あとは [作成] ボタンを押せば自動的に実行形式を含むzipファイルを作成してくれます(圧縮までしてくれるたぁ何て親切・笑!)
Brainfuck の大きさ
Wikipediaによると開発者Urban Müllerがコンパイラがなるべく小さくなる言語として考案した。 実際、Müllerが開発したコンパイラのサイズはわずか123バイト、インタプリタは98バイトであった。なんだそうなんですが、Schemeで書いたBrainfuckインタプリタの実行形式は何と5.09メガバイトもありました(笑)。何と53倍弱の大きさです(笑)。いやあ、富豪の時代ですねぇ(笑)。
これ、twitterでも笑って言ってたんですが(笑)。5.09メガバイトって事はフロッピーディスク一枚に収まらないんですよ(笑)。何枚くらいになるんだろ・・・まあフロッピー四枚くらいで、90年代前半だとゲームで多くてフロッピー二枚、四枚なんて殆どOS並の「大きさ」なんです。
これやってみたらやっぱ長い間Lisp系言語が人気無かったのは分かりますね。Brainfuckくらいの単純なインタプリタでも書いちゃうとOS並の大きさになっちゃう、ってのは20年くらい前のPCだとマジで死活問題です(笑)。いやあ、今の時代は良い時代ですねぇ(笑)。
ってなわけで、実行形式へのリンクも貼っておきますね。